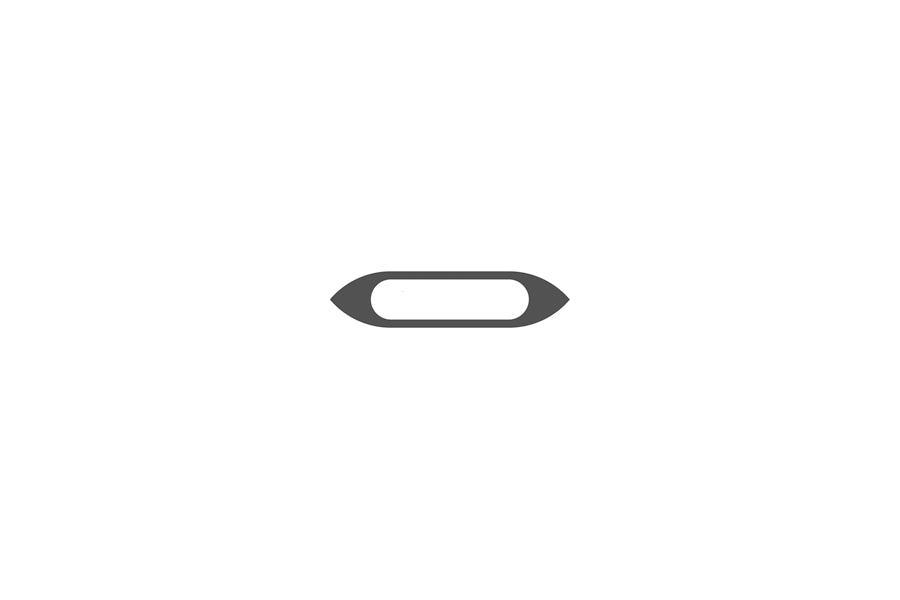『作品』と『きもの』
福本さんが制作しているものは『きもの』と『作品』に大別されます。『きもの』は、私たちが衣服として身に纏うものですが、『作品』と呼ばれるものは、タペストリーをはじめ、空間を表現するアート作品などの大作です。創作過程の違いから『きもの』と『作品』を同時期に併用してつくるのは難しいと仰います。ですが、『きもの』から学び『作品』に活かすこと、また、『作品』の発想を『きもの』へ注ぐことなど、相互関係の大切さも常にあると仰います。『きもの』と『作品』の絶妙なバランスが、福本さんの藍の可能性を更に発展させているのです。なぜ美大西洋学科卒業から『藍染作家』の道へ
単純に「絵が好き」という理由で西洋美術を学んでいた福本さんを藍染め作家へと導いたのには、二つの出会いがあるそうです。 ひとつは、大学在学中にニューギニアへ旅行した際に出会った伝統美術。もう一つは、京都の紺屋でであった藍の色見本糸。
運命的な出会いはどのように訪れたのでしょう。

ニューギニアでの伝統美術への出会い
大学で西洋美術を学んでいた福本さんを伝統美術へ目覚めさせたのは、学生時代に訪れたニューギニア旅行です。約3ヶ月間滞在したニューギニアの、どこの村でも、自分達の民族のための、自分達にしか作れない土器や太鼓、衣服を作っているという自然な生活の営みに、ハッとしたのだそうです。「なぜ自分は日本人に生まれたのに、アメリカンアートやヨーロピアンアートに追随することばかりしているのだろう?」という疑問を初めて持ち、「私は、自分の国の伝統を知らない。日本の伝統を知りたい」という思いに駆られたそうです。その後、福本さんは、京都西陣の機屋さんのもとで学び始めます。藍との出会い
福本さんが勤めた機屋は、正倉院などの復元に熱心に取り組んで、いいものをつくりたいという熱意のもと、腕のよい職人が集まり、そして育っていったといいます。そのような環境の中で、たまたま訪れた紺屋で藍染めの色見本の糸に出会ったのだそうです。色見本の糸とは、藍をどの濃さ、どのような色合いに染め上げるかを決めるための見本に過ぎないものでしたが、福本さんにとっては、その色見本糸こそが、まさに藍の「可能性」そのものでした。 それまで、藍染めを全く知らなかったわけではありません。色見本糸として用意された薄い色から深い紺の色まで広がる藍のグラデーションに、「強さ」「透明感」「奥深さ」を感じ、藍の表現は大変豊かで、表現するのにおもしろい素材と、それからの制作の方向性を決定付けるものになりました。奇跡のトルファン綿

日本で古くから素材として用いられてきた麻が今では大変貴重になったように、綿も例外ではない思っていたところ、トルファン綿に出会いました。「これほどすばらしい生地はない」と惚れ込み、そこにあった白生地すべてを譲り受けたそうです。手作業で採ったトルファンの綿、日本の最高技術で作られた糸、丹後の絹機で織った綿の白生地。
なぜ福本さんの藍染めは澄んでいてきれいなのでしょう?
「澄んでいてきれいなものをつくりたいと自分自身が望んでいるからできるのね」と仰います。「アートは勉強してきたけれど、染めは勉強していない」ノウハウを知らなかったから、造形意識を優先できたのね」柔軟な逆転の発想、形にとらわれず、自分の表現したいものを生み出すために、どうやったらいいだろうか、どんな方法があるだろうかと常に考える。それが、福本さんの原点でした。伝統とは
「伝統」について、福本さんの姿勢は明確です。伝統とは、その時代の、最も最先端なアバンギャルドなものが、伝統として残っていく。
前の時代のアレンジや、古い時代のものを敬い追随するだけではなく、今だからこそ使うことができる新しい技術を取り入れながら、今の環境を最大限に生かす努力をすること。それが伝統をつくっていくことだと仰います。

作品づくりに大切なこと
1.シンプルであること 2.新鮮であること 3.深さがあること 大切なのは新鮮であること、それはつまり、新しいものであること。その時代の素材を、その時代の道具(技術)を使ってつくる。福本さんが、素材や道具にこだわるのは、「伝統」を意識するからこそなのです。手で考える
「頭で考える」だけでは、うまくいかないといいます。作品づくりを進めながら「手で考える」ことが必要です。造形意識を持って表現に重きを置く。そして、藍や技法に振り回されることなく、イメージを形にしていく新鮮さが楽しい。技法をやりこなすのではなく、半歩でも先に進んだことがしたい。どきどきして作品をつくりたい。そうお話される福本さんの前を見据えた強い意志と、柔軟な姿勢は、福本さんの藍の幅広さやしなやかさに共通しているように感じました。 さて、参加頂いたお客様と談話の時間になり、銀座もとじでも大変人気の福本さんのトルファン綿の話題になりました。お仕立てしてお召し頂いてこそその良さを実感する福本さんが藍で染めたトルファン綿。シワになりにくく、着心地が良い。色落ちしない深い藍の光沢。伝統とモダンが共存する福本さんの『きもの』には、衣服としての機能性とファッションとしてのトレンドといった私たちを満足させてしまう秘密があります。
最後に、福本さんから、コーディネートのアドバイスも頂きました。「着物に、何色の小物を合わせるのがお好きですか」という質問には、「今は、モスグリーン。でも、白や紫、黄などもよく合います」とお応え頂きました。透明感のある澄んだ藍には、色が引き立つ。福本さんの『きもの』の奥深い魅力がそこにあります。
2時間に亘って開催されました今回の「もとじ倶楽部」。『きもの』という伝統美術の世界に身を置きながら、常に新しいものを開拓していく「新鮮さ」。福本さんの「藍」の魅力について何かを感じていただけたとすれば、うれしく思います。
ご参加いただきました皆様ありがとうございました。
さて、参加頂いたお客様と談話の時間になり、銀座もとじでも大変人気の福本さんのトルファン綿の話題になりました。お仕立てしてお召し頂いてこそその良さを実感する福本さんが藍で染めたトルファン綿。シワになりにくく、着心地が良い。色落ちしない深い藍の光沢。伝統とモダンが共存する福本さんの『きもの』には、衣服としての機能性とファッションとしてのトレンドといった私たちを満足させてしまう秘密があります。
最後に、福本さんから、コーディネートのアドバイスも頂きました。「着物に、何色の小物を合わせるのがお好きですか」という質問には、「今は、モスグリーン。でも、白や紫、黄などもよく合います」とお応え頂きました。透明感のある澄んだ藍には、色が引き立つ。福本さんの『きもの』の奥深い魅力がそこにあります。
2時間に亘って開催されました今回の「もとじ倶楽部」。『きもの』という伝統美術の世界に身を置きながら、常に新しいものを開拓していく「新鮮さ」。福本さんの「藍」の魅力について何かを感じていただけたとすれば、うれしく思います。
ご参加いただきました皆様ありがとうございました。

 名古屋帯
名古屋帯
 袋帯
袋帯
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 訪問着・付下げ・色無地ほか
訪問着・付下げ・色無地ほか
 浴衣・半巾帯
浴衣・半巾帯
 羽織・コート
羽織・コート
 肌着
肌着
 小物
小物
 履物
履物
 書籍
書籍
 長襦袢
長襦袢
 小物
小物
 帯
帯
 お召
お召
 小紋・江戸小紋
小紋・江戸小紋
 紬・綿・自然布
紬・綿・自然布
 袴
袴
 長襦袢
長襦袢
 浴衣
浴衣
 羽織・コート
羽織・コート
 額裏
額裏
 肌着
肌着
 履物
履物
 紋付
紋付
 書籍
書籍